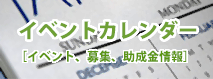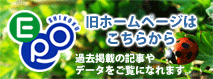特定非営利活動法人由良野の森 / Designated NPO Yurano no Mori / 特定非营利活动法人由良野之森
■生きものと共生し、活力を得るフィールド
愛媛県久万高原町二名地区の山間にありながら、県内外といわず、国内外から多様な人々が集う由良野の森。印象的な赤茶色の壁のゲストハウスのかたわらには小さな流れがあり、オタマジャクシやヤゴなどの水生昆虫もいるなと見ていたら、放し飼いのニワトリがそばで何かをついばんでいます。その先の小屋にはヒツジも。さらに小道を進むとクワの林と天然林、少し登るとスギ・ヒノキの人工林など、いろんな植生があり、わくわくしながら森の散策を楽しめます。
よい季節になると、子育て支援の団体が森のようちえんを開催したり、企業がCSRや職員の福利厚生として里地や森林の整備活動を行ったり、ゲストハウスにはお遍路さんや口コミでやって来る旅行者が宿泊したり。程よく人の手が入った自然の中でゆったりと過ごし、リフレッシュするフィールドであり、様々な人との出会い場にもなっています。
一方、中山間地域の集落での暮しは、過疎化が進むことによって地域の担い手としての負担が増える中、イノシシやシカなどの獣害が拡大し、気候変動による大雪や大雨などが多発傾向にあり、地域の持続可能性に不安を感じることが少なくないといいます。このように山積する課題の中でも、50年先を展望して「今着手しなければ」と、由良野の森が推進するのが、「ブナの森づくりプロジェクト」です。

由良野の森のそばを流れる川で沢のぼり!
■ブナの森づくりプロジェクト
全国的に奥山まで人工林が広がっていますが、適切な整備が行き届かなければ、下層植生が失われ、保水力が低下することなどによって、斜面が崩壊して水害をもたらすなどの危険が高まります。そこで、人間が管理しなくても生態系が持続する、かつて奥山にあった自然林の再生を目指す「ブナの森づくりプロジェクト」をスタートさせました。
森の復元を加速させるためには、人工林の伐採跡地に苗を植える必要があります。そこで、その地域にもともとある樹種を選び、種子を採取し、播種し、苗を育てることに取り組んでいます。さらに、復元地の整備、定植、管理に至るまで、地道な取組を展開することとなります。そのために大切にしていることが、多様な立場やスキルを持つ人・組織との協働。例えば種子採取においては、フリースクールや森林保全を行うNPO、アウトドアショップともコラボして、各地の奥山で種を採取しました。育苗については、水やり等の管理を福祉サービス事業所に委託し、障がいのある人の仕事を作り出しています。また、植物や森林の研究者の協力を得て、科学的な知見に基づいて活動を計画し実証するとともに、山林の所有に関する様々な問題には、弁護士や司法書士などの専門家と解決に取り組む体制を構築しています。
関わった人・組織が、奥山の現状や中山間部を守る生活について知り、ともに考えて活動することを通して、それぞれの立場で持続可能な森づくりの担い手となることが大切であると考えているのです。

フリースクールの仲間たちと種拾い
■森の復元を横展開
50年後の社会構造や環境を想定しつつ、中長期のビジョンとしては、放置林の問題、山林における土地所有の問題、木材利用の付加価値の創出など、様々な社会課題も同時に解決する森づくりを目指し、自然再生推進法のもとで、自然再生協議会を立ち上げる方針です。
そして、全国でも森林の整備・維持については同様の課題があるため、まずは四国で「ブナの森づくりプロジェクト」の手法を横展開することを目指し、令和5年2月に「ローカルSDGs四国」において分科会「四国の奥山自然再生協議会準備会」を発足させました。
※ローカルSDGs四国(LS四国)https://ls459.net/
※分科会「四国の奥山自然再生協議会準備会」https://ls459.net/?page_id=4358

森の復元プラットフォームセミナーの様子
自然の中で過ごす時間に興味がある方、由良野の森では、初めてでも参加しやすい「森のおさんぽとおはなし会」などを定期的に実施しています。森から活力を得るとともに、自然との関わり方を見つめなおす機会になるでしょう。
※由良野の森HP https://yuranonomori.jp/
Designated NPO Yurano no Mori
■ Finding Renewal Through Coexistence With Nature
Located in the mountainous Nimyō district of Kumakōgen, Ehime, Yurano no Mori attracts a wide variety of visitors from both inside Japan and abroad. Near the guest house and its striking reddish-brown walls, a small stream flows, teeming with tadpoles, dragonfly larvae and other aquatic life. Alongside it, free-range chickens peck at the ground, while a sheep pen stands in the distance. Advancing further along the path reveals mulberry and naturally regenerating forests, and beyond that, planted forests of Japanese cedar and Japanese cypress. With such a diverse range of vegetation, guests can enjoy exploring the forest with a sense of excitement.
In favorable seasons, childcare support organizations run a forest kindergarten, companies engage in forest maintenance activities to promote CSR and employee welfare, and the guest house hosts pilgrims and travelers drawn in by word-of-mouth advertising. Nature, thoughtfully cultivated by human hands, provides a space for relaxation and rejuvenation, while fostering connections between visitors from various walks of life.
On the other hand, the growing burden of depopulation on the residents, alongside expanding wildlife damage from boars and deer and an increase in severe weather events like heavy snow and rain due to climate change, has raised concerns about the sustainability of rural mountain life. Nevertheless, even in the face of these challenges, Yurano no Mori is looking ahead to the next fifty years and taking a “now or never” approach, moving forward with the Beech Forest Creation Project.

<Stream climbing in the river by Yurano no Mori!>
■ Beech Forest Creation Project
Although planted forests have proliferated throughout the country, even deep in the mountains, without proper care and maintenance their understory vegetation will be lost, and the reduced water retention capacity can lead to an increased risk of slope failure and flooding. In response, the Beech Forest Creation Project was initiated to restore the naturally regenerating forests that once thrived in these deep mountain areas, which are capable of sustaining themselves without human intervention.
To accelerate the forest’s restoration, it is necessary to plant saplings at the logging sites of planted forests. Efforts are underway to select species native to an area, gather seeds, sow them and raise the saplings. Not only that, serious consideration is being given to the preparation, cultivation, and management of the restoration sites. That’s why collaboration with people and organizations possessing a wide variety of perspectives and skills is vital. For example, seeds native to the mountains of various areas were gathered with the cooperation of Free Schools, forest conservation NPOs and outdoors shops, while tasks such as watering the seedlings were outsourced to welfare service offices, providing job opportunities for people with disabilities. Additionally, all activities are planned and validated based on scientific insights with the assistance of botanists and foresters, and there is a system in place to work together with legal experts such as lawyers and judicial scriveners to address various issues related to forest ownership.
It’s considered essential for all involved parties to learn about the current state of the deep mountains and lifestyles that preserve mountainous areas, and, through thinking and working together, to become stewards of sustainable forestry in their own ways.

<Gathering seeds with Free School partners>
■ Scaling It Out
While forecasting the social and environmental landscape 50 years in the future, the mid-to-long term vision includes a plan to start a Nature Restoration Council under the Law for the Promotion of Nature Restoration in order to tackle various societal challenges such as the issue of neglected forests, land ownership in forested areas, and the creation of added value through timber use.
Also, because similar challenges in forest maintenance and preservation exist nationwide, the goal is to scale out the methodologies of the Beech Forest Creation Project, starting with the rest of Shikoku. To that end, in February 2023 the “Shikoku Deep Mountain Nature Restoration Council Preparatory Committee” was established as a subcommittee under Local SDGs Shikoku.
※Local SDGs Shikoku(LS Shikoku)https://ls459.net/
※ Subcommittee “Shikoku Deep Mountain Nature Restoration Council Preparatory Committee”
https://ls459.net/?page_id=4358

<Scene from the Forest Restoration Platform Seminar>
For those interested in spending time in nature, Yurano no Mori holds regular events that even beginners can enjoy, such as the “Forest Walk and Talk.” These outings provide an opportunity to draw energy from the forest and reconsider one’s relationship with the natural world.
※Yurano no Mori Official website https://yuranonomori.jp/
特定非营利活动法人由良野之森
■与生物共生,获得活力的场所
由良野之森虽然坐落在爱媛县久万高原町的二名地区的山间,却聚集了来自国内外的各种各样的人士。带来深刻印象的红褐色墙壁的民宿旁边有一条小河,河里有蝌蚪、水虿等水生昆虫,放养的鸡在旁边啄着什么。在它的前面的小屋里还有羊。再往前走,在小路上就能看到桑树林和天然林,再往上登高一些,就能看到杉树和柏树组成的人工林等,有各种各样的植被,可以尽情享受在森林里散步的乐趣。
一到好季节,育儿支援团体就会开办森林幼儿园,企业作为履行社会责任和给予职员的福利,也会在这里开展周边土地和森林的整备活动,民宿也会有通过参加四国遍路活动的遍路客和因口碑评论而来的游客入住。由良野之森能够让人在适度人工处理过的自然中悠闲生活,是得以放松精神的地方,也是与各种各样的人相遇的场所。
另一方面,在山间地区的村落的生活,由于人口过疏化的加剧,作为该区域(由良野之森)的负责人的负担也在增加:野猪和鹿等野兽的危害在扩大的同时,由于气候变化,暴雪和大雨等气象灾害也有多发的倾向,(由良野之森的负责人)对地区的可持续性感到不安。在堆积如山的课题中,由良野之森在展望50年后,认为“必须着手于现在”,从而推进了“山毛榉林建设项目”。

<散步在良野森林旁的河畔!>
■山毛榉树林建设项目
虽然全国范围内的深山内都有人工林,但是如果不进行适当的维护,由于下层植被丧失,保水能力下降等原因,导致斜坡崩塌并造成水灾的危险也会提高。因此,即使人类不进行管理,生态系统也能维持的,过去深山中自然林的再生为目标的 “山毛榉树林建设项目”启动了。
为了加速森林的复原,有必要在人工林的采伐地点种植幼苗。因此,开展了选择当地原有的树种,采集种子,播种,培育幼苗的工作。并且,从复原地的整备、定植到管理,都要逐步仔细的实施。为此,最重要的是与拥有不同技能的人、有组织的协同工作。例如,在种子采集方面,与自主教育学校、开展森林保护的非盈利组织、户外运动商店合作,在各地的深山采集种子。关于育苗,浇水等的管理委托给福利服务事业所,为残疾人创造了工作。此外,在植物和森林研究者的协助下,基于科学知识对活动进行计划和实证的同时,针对与森林所有权相关的各种问题构建了与律师、司法书士等专家共同解决问题的工作体制。
(由良野之森)认为,相关的人和组织要了解深山的现状和保护山中环境的生活方式,通过共同思考并开展活动,站在不同的立场上,成为可持续发展的森林的责任者。

<自主教育学校的伙伴们和拾种籽>
■森林复原的横向展开
在设想50年后的社会结构和环境状况的同时,作为中长期的方向,为实现同时解决放置林的问题、与山林有关的土地归属的问题、创造木材利用的附加价值等各种社会性课题的森林建设,在自然再生推进法的基础上,设定了创建自然再生协议会的方针。
并且,由于全国森林的整备·维持也有同样的课题,因此以将首先在四国开展的“山毛榉林建设项目”的方法横向展开为目标,令和5年2月在“Local SDGs(地域循环共生圈)四国”组织内,成立了作为分科会的“四国的深山自然再生协议会筹备会”。
※Local SDGs(地域循环共生圈)四国(LS Shikoku)https://ls459.net/
※分科会“四国的深山自然再生协议会筹备会” https://ls459.net/?page_id=4358

<森林的复原平台研讨会的样子>
对于对在大自然中度过的时间感兴趣的人,在由良野之森,会定期举办即使是第一次也很容易参加的“森林的散步和聊天会”。在从森林中获得活力的同时,也是重新审视与自然相处的方法的机会。
※由良野之森官网 https://yuranonomori.jp/